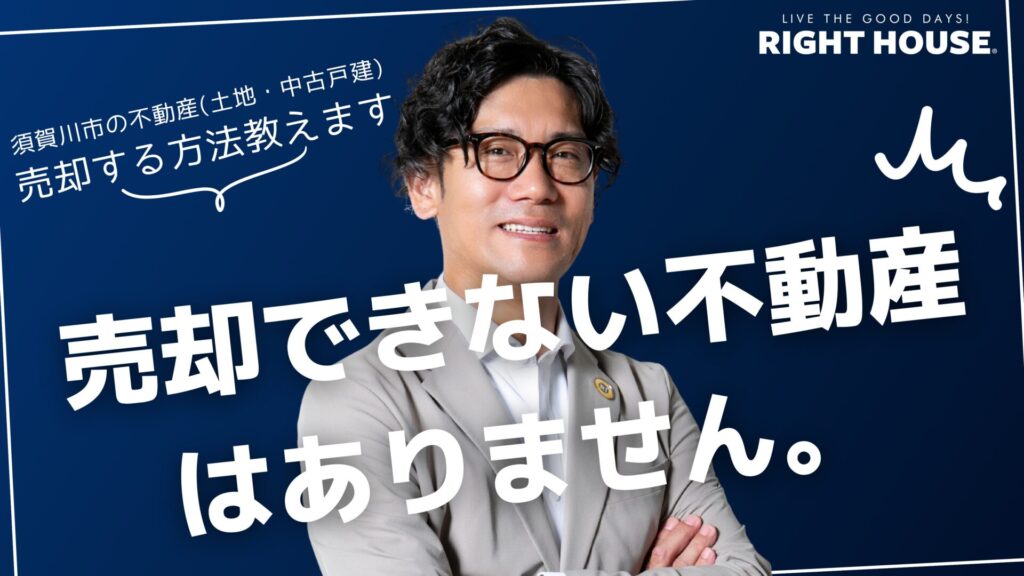インスタでも発信中☞https://www.instagram.com/p/DPlfQmEiXe8/?img_index=1

Q.親父が認知症で施設から戻らないので実家を売りたいが、問題ない?
認知症になった親の不動産は売却できる?
認知症で判断力が低下してしまうと財産管理や生活面の手配などで困ることが多くなります。そんな時に便利な制度が「成年後見制度」です。
今回は、成年後見制度についてわかりやすく解説します。
成年後見制度とは
判断力が低下した人の財産や生活を守る制度。「後見人」というサポート役を選び、後見人は本人の意思に沿って法律行為を代行したり、相談したりします。成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
「任意後見制度」と「法定後見制度」それぞれの特徴は次の通りです。
任意後見制度・法定後見制度
任意後見制度
判断能力が衰える前に自分で選んだ任意後見人に生活や財産の代理権を与える制度です。公正証書で契約します。
法定後見制度
家庭裁判所が選んだ成年後見人などが本人の代わりに契約や取り消しを行える制度です。判断能力の低下具合で後見・補佐・補助の3つに分かれます。
任意後見の申し立て手続き
①本人が任意後見人を選ぶ
個人や法人ができます。複数人でもOK。
②契約内容を決める
任意後見人に依頼する内容は、当事者が自由に決められます。委任できるのは、財産管理や介護・生活面の法律行為と登記です。
③公証役場で任意後見契約を結ぶ
本人の居住地近くの公正証書を作成
④必要書類をそろえ、家庭裁判所で申し立て
本人の判断能力が低下したら、本人の居住地を管轄する家庭裁判所に「任意後見監督人の選任の申し立て」をします。申し立てできるのは本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者です。
⑤家庭裁判所が任意後見監督人を選任する
任意後見契約は東京の法務局に登録が必要。「登記事項証明書」をもらうことで自分が代理人だと他に示すことができます。
法定後見で後見人を決める手続き
①後見開始の裁判を申し立て
②家庭裁判所の調査官による調査
話を聞いたり医者が判断力を調べたりする。補佐・後見は判断力の鑑定が必要
③後見等開始の審理・審判
裁判所が後見を始めるかと、後見人を決定
④後見等開始の審判確定と登記
成年後見人が不動産を売却する方法
売却する不動産が居住用不動産か非居住用不動産かで方法は変わります。居住用不動産の売却には裁判所の許可が必要です。非居住不動産の売却は裁判所の許可は不要ですが、念のため相談しておくことをおすすめします。
居住用か非居住用か分からない場合裁判所に相談するのがおすすめです。
親が認知症になっても、成年後見制度を利用すれば親の不動産を売却することは可能です。親の不動産を売却するときは、信頼できる不動産会社に依頼することが大切です。